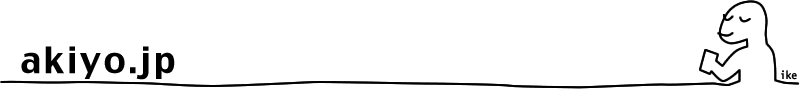2006.12.12
スーパーエッシャー展
先日、打ち合わせの帰りにスーパーエッシャー展を見てきました。おもしろかった!
あまりにも有名な「だまし絵」もさることながら、それよりも前の時代の作品も多数展示されていて見応えがありました。
前にもどこかで書いた気がしますが、私は「全盛期を迎える直前」というのがとても好きなのです。双葉が種の殻を破って「ぷりん!」と伸びる直前とか、ホウセンカの種がはじけ飛ぶ直前とか。そんな感じの潜在力を蓄えている状態です。
それはさておき。
多くの作品中で使われている色は「白」と「黒」に限定されています。通常「白の粒」と「黒の粒」を小さくすればするほど、現実風景に近い表現が可能なるでしょう。ところが、曖昧なグレーを廃して「白の塊」と「黒の塊」で表現しようとすると、抽象化する必要が生じます。
光と陰の表現は、ストライプの間隔の違いや、ギザギザや、稜線の強調といったものに美しく変換されているのです。
また、作品中メインで扱っているモチーフを飾り縁などで反復して用いているのも面白いのです。
幾何学嗜好が強く出ているところも、幾何学好きにはたまりません。
幾何学といえば。「うずまき」を使って音階を視覚化している作品もありました。音階をうずまきに変換するのは思いつかなかった。すごい。そして、音の波長とオクターブの関係を考えると、凄まじく理にかなっています。
この企画展は1月13日まで開催される予定のようです。ものすごく込んでいると思いますが、興味のある方はぜひ!
余談ですが。レゴでエッシャーに挑戦した作品。作れちゃうんですねぇ。
スーパーエッシャー展
Bunkamura ザ・ミュージアム
2006年11月11日(土)〜2007年1月13日(土)
2006.12.2
なんだか偏屈っぽそう。
マイミクさんが紹介していた「タイプ別性格判断」をやってみました。
INTP型:問題を解決したがる
考えにふけってうわの空の大学教授を絵に描いたようなタイプがINTP型である。
頭の中でじっくり考える(I型)なので、N型の想像力がいろいろな可能性を思いつく。
客観的(T型)なので、その新しいデータを分析し、際限なく融通がきく(P型)ので、どんなデータもさっそく取り入れてしまう。
論文、図面、計画、企画、提案、理論などなんであろうと、こまごました情報を一つにまとめた完成図を作りあげようとするが、たえず新しいデータを発見するので、その完成図がどんどん膨らんでしまう。
その結果、考えや構想や計画がどんなに最終的なものに見えても、土壇場になって「新しいデータ」が手に入ると変えてしまうのである。
これはINTP型にとってはわくわくするほど楽しいが、ほかの人、とくにJ型の性向を持つ人にはフラストレーションになる。
完璧に見えても満足しないので、みずからが最大の批評家となり、あら探しをする。
完璧、有能、優秀であろうとするあまり、それが極端になると、かえって負担になり、うんざりしたり自分を責めたりする。
このタイプは女性の場合に葛藤を生む。
考えにふける大学教授というのは従来、女性のイメージというよりは男性のイメージで、頭だけで理屈をこねる資質は、男性の場合は大目に見られるが、女性の場合あまり受け入れられない。
そこで少なくとも三つの問題が生じる。
第一に、女性は昔から、家庭や家族のこと以外では設計能力があるとは見られてこなかった。
だから、人生を頭で考えた理屈にあわせたいと思うのは、INTP型にとっては当たり前なのだが、従来の女性の役割には真っ向から反する。
第二に、独創的に考えるのも従来の女性の気質とは見られていない。
たとえば、時間を聞かれると、INTP型は時間の哲学的な意味について述べたくなる。
そうした風変わりな面も男性ならば頭がよすぎるせいだと見られるが、女性だと「鈍感」とか、ときには「頭が鈍い」というレッテルをはられてしまう。
第三に、T型の面が、従順、優しい、気配りといった女らしさに反する形で表れる。
INTP型の女性が感情を表にあらわした場合、悪くすると、しばしば極端に表現しすぎて、本人もほかの人もぎょっとしてしまう。
うううーーん。。。。
やっぱり私は女に向いていなかったのかぁ???(←軽く動揺中)
とはいえ、結構グサグサとあたってるような気が・・・。
2006.11.27
陽光の音色
笙という楽器がある。
「ふやーーうぁ〜」という感じの音で
複数の音程の音を同時に奏でることが可能。
その音色は「陽光が差し込む感じ」を表現しているという。
* * *
ダニ・カラヴァンの「シャルル・ドゴールの遊歩道」の作品のデータより。
素材:
陽光、水、培養土、草、木、風、木、ブルー・アスファルト、白コンクリート、鉄、レール、ガラスの立方体、文字
リストの最初に「陽光」を挙げている。
「この作品は太陽の光を受けてはじめて完成するのさ」
そんな意図が感じられる。
この作品以外にも、様々な彼の作品の中で「陽光」は使われている。
たしかに、彼の生み出すシンプルな形状は
太陽の光をあびて
それもかなり強い日差しの元で、
光と陰の強烈なコントラストをまとうと
実に良く映える。
* * *
ニュートンはプリズムを使って陽光を分析した。
一見、無色透明で
物体にあたると濃い影を発生させるその光には
様々な波長(=色)が含まれることを実証してみせた。
虹も青空も夕焼けも、
陽光が含む様々な色が生み出しているのだ。
* * *
話を「笙」に戻そう。
その音色を「陽光」と感じた我々のご先祖は
(もしかしたら日本人としてのご先祖ではないかもしれないけど)
「太陽の光には様々な波長(→色→波→音程)が含まれる」なんてことは
知らなかったのではないか。
「なんとなく、おひさまの光みたいな音だね」
一人の素晴らしい感性を持った人物の一言から、
陽光の音色を表現できる楽器として
語られるようになったのかもしれない。
波長云々は別にしても
笙から奏でられる音からは、
竹林の葉の隙間から降り注ぐ太陽の光を感じる。
* * *
「笙の音は陽光の音」
含まれる波長の多様性を知ってか知らずか、
そう表現したイニシエの人の感覚は、実に素晴らしい。