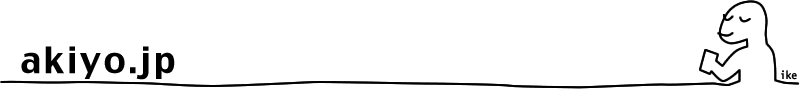2005.9.8
N進数
人間の指は5本。両手あわせて10本。
これが10進数が最もメジャーになった主な理由なのでしょうか。
そもそも何で人間の片手の指は5本なんでしょう?
以前、聞いたことがある話によると、
魚の「手」に進化した部分にあたる骨の状態が
「5本指」だった、とか。
しかも「6本指」の魚が多い中、
たまたま「ほ乳類」まで進化した種が5本指だった、なんて話も。
ヒマラヤの麓の部族だったと思うのですが。
その村の人たちは、なぜか6本指の人が多いとか。
「6本指の魚の末裔」と考えるべきか?
「突然変異」と考えるべきか?
* * *
なーんとなく、なんですけど
5進数系、主には10進数はフィジカルな要素、
6進数系、主には12進数はメンタルな要素が強い気が。
メンタル、っていうのは少し違うかもしれませんが。
さらに言えば、5進数系はアリストテレス系、
6進数系はプラトン系、とか?
* * *
5進数がメジャーになった理由は、
やはりヒューマン・スケールに起因する気がします。
指を折って数えるのにも便利ですしね。
でも、2進法を使えば慣れれば片手で31まで数えられます。
この方法は、小学生の時に水泳の先生に教えてもらいました。
当時はこれが「2進法」だなんて知らなかったけど。
親指→1
人差し指→2
中指→4
薬指→8
小指→16
これで数えてみてください!
* * *
それに対して6進数、
特にその系統の12進数は天文的要素、
あるいは時空的要素を得意としている感があります。
太陰暦・太陽暦などの暦とか。
1年は12の月で一巡していきます。
「星占いは天文学のおろかな娘」と言ったのは
ケプラーだったでしょうか?
その星占いも12に分かれています。
天空の360度、
この数値設定自体、含まれる素因数から
フクザツな意図を感じますが、
それはさておき。
その、いかようにもとれる360度の黄道上の星座を
12ピックアップしたワケも暦的束縛があるのでしょう。
音の12律も、
オクターブと呼ばれる波長、あるいは周波数が2倍になる音域を
12に分割したものです。
「12に分割したもの」という言い方は厳密には違います。
この音階は、あまりにも美しいシステムによって
(何度もこの話してすみません〜。
でも、本当に感涙的に美しいシステムだと思うんです!!!)
「12の音を設定せざるを得なかった」と言えると思うのです。
なにも西洋の音楽に限ったことではありません。
日本の音楽にも12の音律があったようです。
* * *
なんだか、6進数系を過度の思い入れで語っている気もしますが
ともかく、5進数系は人間の皮膚の内側の出来事、
6進数系は皮膚の外側の出来事に影響されていると言えそうです。
* * *
5進数と6進数のイイトコドリをしようとすると
必然的に30という数が浮かび上がります。
1ヶ月の日の数はおおよそ30。
でも、山頭火的字余り・字足らず状態なので
「30」と断定するには無理があります。
もうちょっと拡大して60にすると?
世界的に一番有名なのはマヤ歴あたりでしょうか?
日本の暦も「十干」と「十二支」を組み合わせれば60年で一巡します。
* * *
フと思ったのですが、英語で12(twelve)までは独自のカタチを持つのは
12進数の名残なんでしょうか?
フランス語では16(seize)までカタチが違うところを見ると、
2進数系文化圏だったのでしょうか?
日本語は漢数字を見るかぎり、わかりやすく10進数系ですね。
コンピュータさんの都合では2進数が一番便利だったようですが、
文化人類学的に進数を見ていくと、
見落としてきてしまった様々なことが見えてきそうです。
2005.8.29
音あそび
1. 金属でできた入れ物を用意。鍋でもヤカンでも鍋のフタでも可。
2. それを流しのフチかどこかにぶつける。
3. 「かぁぁぁ〜ん!」と音がする。
4. 「かぁぁぁ〜ん!」の残響が残っているうちに、すかざず入れ物に水を注ぐ。
5. 残響が「くワぉぉぉぉ〜ん?」と変化する。
シンプルだけど、ちょっと楽しいです。(^_^;)
気が向いた方、試してみて〜!
2005.8.22
リエゾンとコンニャク
フランス語が厄介な理由の一つにその単語の読み方の変化、というものがあります。具体的には「リエゾン」「アンシェヌマン」「エリジオン」という名前のついた法則です。
例えば。
Vous aves une auto?
「車を持っていますか?」という文章。
単語で読むと「ヴ」「アヴェ」「ユヌ」「オート」という言葉が、文章としてつながると「ヴザヴェユノート」という具合にズルズルっと混ざり合ってしまうのです。
ま、これはフランス語に限らず、他の言葉でもあることです。英語だったら「in a box」を「イン・ア・ボックス」ではなく「イナボックス」というように読んだり、岡山弁だったら「ワシはね」が「わしゃーのォ」になったり。(ああ、ローカルな例え!)
それにしても何にしても。前後の言葉で混ざり方が変わってくるので、初心者としては、かなーり混乱してしまうのです。
でもね。コレって筑前煮のコンニャクに似てるかも?って思ったんです。煮物に入れるコンニャクは、味がしみやすいように手でちぎったりするものですが、なーんとなくフランス語の単語も「お互いに味がしみてる」と思えば暖かい目で見守れるような気もしてきます。
ロンドンのセントラル・パークだっけ?腐ったり痛んだりした木の枝を落とす時に、ノコギリでスパっと切った断面には微生物が繁殖しにくいので、軍隊が実習を兼ねて(!)ダイナマイトで破壊するそうです。そうすることによって、微生物が発生し、虫が住み着き、小鳥もやってくる、という食物連鎖が生まれやすくなるとか。これも「混ざりやすく」した例と言えなくもないかもしれません。
グラフィックスで言えば、グラデーションのようなものです。
映像で言えば、モーフィングのようなものです。
音でいえば、クロスフェードのようなものです。
・・・と、あの手この手でポジティブに考えようとしてみたワケですが、やっぱり。
むーずーかーしーい!(@_@;)
【今日の気になったニュース】
いきなり新コーナーを作ってみました。(^_^;) あまり重要ではないかもしれないけど、個人的に好きなニュースをピックアップしてみようと思います。でも、きっと不定期。
ベトナムで「世界一美しい洞窟」が発見される
世界一かぁ!どんな感じでウツクシイんだろ?いまだに発見されていなかった洞窟があるってのも驚きです。ベトナムも行ってみたいなぁ〜!