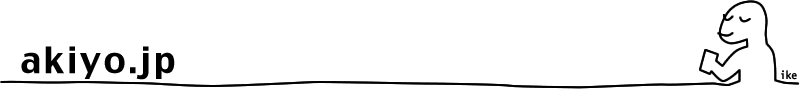2007.3.20
博物館
博物館には死の匂いがつきまとう
かつては命を宿していたものはもちろんのこと
無機質なものでもそう感じる
本来の機能を停止させて
鑑賞されるだけになってしまった物たち
* * *
それは博物館に限らないのかもしれない
平泉の中尊寺に「覆堂」という建物がある
本来は「金色堂」を保護することを目的として建てられた
覆堂の環境は
金色堂を保護するには不十分と考えての処置だろうか
金色堂はコンクリート製の「新・覆堂」の中に移されていた
本来の覆堂はどうしているのだろう
がらん、とした内部を持て余しつつ
そこに建っていた
ポッカリと空いた内部が物悲しい
子供が出ていった後の子宮にも似ている気がした
* * *
パリの地図を広げてみる
誰もが知っているような美術館や博物館が目に入る
さらに、よくよく眺めてみると
町の中には小さな博物館が潜んでいる
「錠前」や「魔法」や「地図」を集めた博物館
個人の名前を冠した博物館
エゾテリスム、なんて言葉を思い出す
この種の小さな博物館は
ロンドンやプラハにも期待できそうだ
もちろん、他の町にも
* * *
個人の強烈な嗜好で集められたものには
時として残存意思のようなものを感じる
分類されている訳でもなく
体系化されている訳でもない
それでも感じる不思議な調和と虚構
古い学校の理科室に似た
埃っぽい硝子ケースにおさめられたものたち
一見、緻密に
一見、無造作に
残存意思と向かい合うのは
その空間だけに留めておきたい
連れ帰ると、とんでもない目にあうから
* * *
小さくて濃密な博物館の番人は
初老の人物がよく似合う
男性でも女性でも良い
「ちょっと、お尋ねしたいのですが」
なにげなく質問してみる
フとした弾みに口をついた言葉
その言葉を聞いた瞬間、番人の目の色が変わる
地味な風貌の彼、あるいは彼女は
気だるく展示案内の冊子を渡してくれた時とは別人のように
静かに語り始める
展示物たちも変化してくる
死の匂いのするヌケガラ?
とんでもない!
死んだフリをしていただけだったのだ
2007.3.18
「地球が自転するの見に来られたし」
『フーコーの振り子』を読みました。
と言っても、ウンベルト・エーコの大作ではなく、アミール・D. アクゼルによるレオン・フーコー自身についての本
の方。
エーコ版はずいぶん昔に読んで、かなり面白かった記憶があります。でも、再読するのは覚悟がいりそうです。
それはさておき。
今回読んだ『フーコーの振り子』も面白かった!ほぼ1日で一気に読了してしまいました。近代史や科学史に詳しい方にはそれほど目新し内容ではないのかもしれませんが。
レオン・フーコー(1819年9月18日-1868年2月11日)
振り子を使って地球が自転していることを証明した。
こんな教科書に載ってそうな説明だけでは見えてこない、その偉業に至までの数世紀にもわたる科学者たちの苦難や歴史背景が語られているのです。
しかも、かなり読みやすい。
フーコーをとりまく多くの人々、代表的なところではナポレオン三世やフランソワ・アラゴーなどが登場するのですが。まず外堀を埋めていくように、かの人々のそれまでの生き方なり人となりが語られ、自然に本筋であるフーコーの話に編み込まれていく、その語り口が絶妙なのです。自然に読み進めていくことができます。(しかも、「アクゼルさんは、ガリレオ・ガリレイが嫌いなの?」と言ったツっこみを入れたくなるような記述が出てきたり:笑)
フーコーって、実は独学で科学を学んだ人だったんですね。知りませんでした。そのため、排他的で権威的なアカデミーに、なかなか認めてもらえない憂き目にあってきたようです。それでも彼には実験機材を発明する器用さと知識、視野の広い科学についての洞察力、それを分かりやすく表現することのできる文章力という武器がありました。
さて、タイトルの「地球が自転するの見に来られたし」ですが。
これは、ついに振り子よって地球に自転を証明する実験に成功した彼が、フランソワ・アラゴーのバックアップのもと、パリ在住の科学者という科学者に送った公開実験の招待状に記された文なのです。こうして「美しい実験」のための準備は整いました。
『フーコーの振り子?科学を勝利に導いた世紀の大実験
なんともシンプルで美しい実験ではありませんか!
余談ですが「公開実験」って響き、良いですね。未知の世界への好奇心と、期待感と、そして若干の胡散臭さが混在している感じで。
2007.3.11
幽体離脱式タイムスリップ
・・・と言っても夢のお話。
実体はそのまま現代に残って
魂だけがすーっと抜けていく。
これなら別の時代に行っても歴史は変わらない。
よくできてるなぁ、と夢の中で感心した。
始めてのタイムスリップで行ったのは
江戸時代だった。
お百姓さんが鍬で畑を耕している。
それを私の意識はプカプカと宙に浮いて見ていた。
一日中、見ていた。
二度目は平安時代。
なぜか紫式部の頭の中に入っていた。
日々、生活する。
物語りを組み立てる。
それを書く。
そんな日常。
三度目は長い夢だった。
インカ文明が発生してから滅亡するまでを見た。
最初は小さな集落だった。
少しづつ人が集まりはじめ、
そしてあの、
今では遺跡になってしまっている建造物を造るまでに成長する。
文明は繁栄する。
しかしそれもスペイン人がやってくるまでのこと。
偉大な文明は消えた。
目が覚めた時、私は泣いていた。
そんな夢を見ていたのは、私がまだ高校生だったころのこと。
その後、見た覚えはなかった。
それが今朝、久しぶりにタイムスリップの夢を見た。
それも、初めて未来へ行ったようだ。
文明崩壊後の世界、らしい。
人はまばらだった。
それでも意外とのどかに生活している。
一人の男に会う。
植物の絵を描いていた。
画家、というよりも
イラストレーター、と言った方がよいかもしれない。
そんな作風だった。
画面いっぱいに植物を描いていた。
毎日描いていた。
トンネル跡のような場所が、ちょっとした市場になっていた。
市場、というほどの大きさではない。
露店が2つ、3つ、立っているだけだ。
男はそこで買い物をする。
何を買っていたかは覚えていない。
しかし、その時差し出された紙幣は見覚えのあるものだった。
福沢諭吉が描かれた1万円札。
ヒヤリ、とした。
それは、私達の文明がなくなってしまうのは
そう遠い未来の話ではないのかもしれない、
と思わせるものだった。
覚えているのはここまで。
【旧 Short Tripより 2002.06.04】