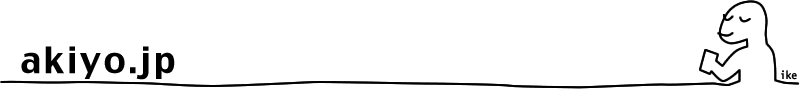カテゴリー:思考の断片
2004.11.12
目測スケール
文章の文字制限で「400字程度で」と言われると、今でも「あ、それだったら原稿用紙1枚分か」なんて原稿用紙換算してしまいます。子供のころ、感想文だの小論文だのといった文章系の宿題が多かったせいかもしれません。
文章に限らず、なーんとなく感覚をつかむために基準にしてしまうものがあります。
■ピアノの1オクターブ
およそ16cm。手のひらサイズのものをイメージする時に便利です。手の小さい私は、手を思いっきり広げても親指の先から小指の先までが19cm。20cm丁度とかだったら便利なのになぁ。
■ペットボトル
2リットル=2キロ。自分で持ち上がられるモノをイメージする時に。「うちの子、○kgになったの〜」なんて友達の話を聞いている時、私の頭の中ではペットボトル換算でイメージされてるはず。
■プール
25mにしても50mにしても、一目で見渡せるものをイメージする時に便利。・・・というはずなのですが、オリンピックだの世界水泳だの観ると、妙に50mが短く補正されてしまったように錯覚します。(笑)
■メトロノーム(0.5秒)
[4分音符]=120という一番よく使うあたりを。心臓の音あたりを基準にする方もいるかもしれませんが、軟弱な私の心臓はすぐに早くなったり遅くなったりシンコペーションしたり(危ない!)したりしてるよーな気がするのであまり参考になりません。(それでも心臓が悪いと言われたことは一度もないので心配しないでください〜(^_^;)
■450px、600px、700px
特に何を基準にしているワケではないのですが、よく使う大きさなのでなんとなく。ちなみにこの「short trip」のタイトル画像の幅は700pxです。
他にもあった気がするのですが、パっと思い出せません。
このあたりの「モノの大きさその他を何を基準にイメージするか?」ということは、人それぞれでおもしろそう!砲丸投げのボールの重さだったり、マージャンパイの大きさだったり、釣り船のモーターの音だったり、自分の親指の爪の幅だったりするんだろうなぁ。
大きなモノを表現するのに、よく「東京ドーム○個分」というたとえを見ますが、私は野球は観ないので、わかったようなわからないような感じです。でも、「なんだか大きいんだね」ということが伝われば十分なのかもしれません。
そのうち、「1光年といえば、ちょうど○○くらいの距離だよね」なんてことが語られる日が来るのかもしれませんね?!
2004.9.3
「もちろん」
「日本人はよく『もちろん(of course)』と言うけど、
時々奇妙な使い方をしていると感じてしまう時があるんだ」
そんな話をしていたのは、スコットランドの人。
「もちろん、私は自分の仕事が好きなんです」という感じにね。
こんな例をあげていた。
「会ってすぐの人なのに、
彼(もしくは彼女)が自分の仕事が好きかどうかなんて
僕にはわからないよ」
もしも、私が聞き手だったら
「ふーん、そう」くらいで聞き流していそうな気がする。
スコットランド人の彼と、何が違うのだろう?
辞書には「もちろん = of course」とある。
でも、その意味に含まれる範囲は若干異なるのかもしれない。
(私の語学力では何とも言えませんが・・・)
もしくは、
日本国民の根底意識に
「勤労は当然だ!」みたいな共通意識があるのかもしれない。
(かなぁ?)
真偽のほどはともかく、
国民的な意識のコンテクストの違いだとしたら、
大げさな話になってくる。
* * *
会話の中だけでなく、デザインの世界では
いかに上手に「もちろん」を使うかは
かなり重要なことだろう。
「この絵をみたら、トイレはココだってわかるよね?」
「この場所なら煙草を吸ってもいいってわかるよね?」
「WEBサイトのこのページの中で、リンクボタンはどこかわかるよね?」
「この箱は、ここから開ければいいってわかるよね?」
などなど。
それを見せる手法はまちまち。
「それらしく」デザインしたり
他の部分の印象を控えめにすることによって
「ココしかないだろう」と見せてみたり。
* * *
でもね。
パブリックな「もちろん」は
ある程度標準化できるかもしれないけど
一番難しいのは個人個人の「もちろん」かもしれないなぁ。
2004.7.4
「勝ち組」「負け組」なんて言うけれど
女子バレーの柳本監督の座右の銘は「負勝」。「負けを知ってるものは勝つことの大変さ大事さをすごく良く知っているんだ」ということだそうです。これが言えるのは、何もスポーツの世界だけではないはずです。
* * *
現在、世界で一番威張っている国で成功している人の先祖の中には、やむにやまれる理由で、しぶしぶ未知の大陸に渡っていった人もいたことでしょう。
その本国の「太陽の沈まない帝国」と言われた国も、ローマ人たちからみれば、ただの田舎の島だったかもしれません。
そのローマでの重要な都市だった町も、ギリシャの新しい入植地から始まったものもあるでしょう。(ちなみにナポリは「ネアポリス=新しい町」というのが語源だと聞いたことがあります)
そのギリシャだって、エジプト人からすれば「海のむこうの新興国」だった時代もあるでしょう。
エジプトをはじめとする、素晴らしい古代文明を築きあげた人類も、上手に木の上を渡り歩く種族に食べ物を奪われて、やむを得ず木から下りて森を出て、危険な平原へと生活の場をうつしていった動物の末裔かもしれません。
その当時から地球を我がもの顔で歩き回っていた「ほ乳類」も、発生した当初は巨大なトカゲたちに踏みつぶされないように、ものかげで息をひそめて暮らしていたこともあったでしょう。
巨大化していったトカゲたちの先祖も、豊かな海の中での生存競争に負けて、危険な丘にあがっていくことになった、というのが本音かもしれません。
海の中でも「食べる側」に成長した動物たちも、細胞ができたころには植物みたいな丈夫な細胞壁をうらやましく思っていたかもしれません。
このように、爆発的な進化をとげていった動物細胞たちも、隕石にくっついて、広大な宇宙を彷徨っていたかったのに、運悪くできたばかりの星に落ちてしまったアミノ酸が元になっている可能性もあります。
・・・そんなことを辺境の島国で思いをめぐらせてみました。