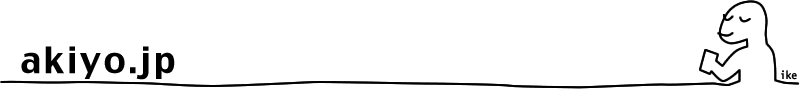2007.6.7
一瞬の緑

少し前にテレビで見た志村ふくみさんのインタビュー。
「草木染めで緑という色を出すのは本当に難しいんです。
自然界の植物は緑色をしているけれど、
染めると緑色ではなくなってしまうのです」
「布を藍に浸して、頃合いをみて引き上げます。
液から出した時、布は濃い茶色なのですが、
空気に触れると、あの藍の独特の色が現れるのです」
「藍を含んだ茶色の布を絞って、手を離した時、
一瞬だけ緑色が現れるのです」
「そのあと、すぐに布は藍特有の色になっていくのです」
「その時現れる一瞬の緑は、
自然の植物本来の緑が、
フと現れているような気がするのです」
言葉の表現はウロ覚えなので、詳細は違っていると思いますが、
こんな感じのことを語っていらっしゃいました。
その後、実際に藍を絞る瞬間の映像が流れたのです。
目をこらして見ました。
瞬きもしないように気をつけながら。
絞っている手を緩めたその瞬間。
はたして緑は現れました。
少し光沢を帯びているようにも見えました。
カナブンの硬質な羽の色にも似た鮮やかな緑が
ほんの一瞬。
2007.6.4
バカロレアの哲学の問題
フランスの大学入試資格、バカロレア。今日のフランス語講座でもその話題が取り上げられていました。
で、驚いたのがその哲学の試験の内容。3つほどの命題の中から好きなものを1つ選んで4時間かけて論述するというのかその内容とのことなのですが。
これ、高校生が答えられる問題?と思うほどスゴイんです。少なくとも私はそう思いました。高校生の自分だったら、絶対答えられそうにないものばかりです。
高校生なら無理でも、それからン年経った今なら?というと、やっぱり難しい問題ばかり。。。それでも無謀にも直感的にチラっと考えてみたいと思います。
以下、ラジオ講座で紹介されていたものの他にコチラのサイトやコチラのサイトで紹介されていたものも含めてご紹介します。3つ目の「文章を読んでコメント」は無理なので、その他の2問をとりあげました。
* * *
■ 芸術作品は背徳的であってもよいか?
それが背徳的かどうか判断するのも芸術家の役割なのでは?と思います。
■ 無償の行為は可能であるか?
可能だと思います。(青いかな?ワタシ。:汗)
■ 情熱は思慮分別と共存できるか?
できるでしょう!(ドきっぱり)
少なくとも、「創作」の場では情熱的な部分とそれを冷静に見つめる部分が同時に自分の中にあるように思います。
■ もし世界に意味がないとしても哲学はなお目的を持ちうるか?
「世界に意味がない」という状況が理解できません・・・。
■ 哲学は諸科学についての考察をせずに済ますことができるか?
諸科学について考察した方が楽しく哲学できると思います。
■ ある芸術作品が美しいということを他人に根拠を示して説得することができるか?
説得されて「美しい」と「納得」するような程度のものであれば、説得された本人にとっては本当には「美しい」ものではないのだと思います。
■ 人は自分自身に嘘をつくことができるか?
必要に応じて。
・・・と言いつつ、あまり必要性を感じたことがないような気も。。。
■ どのような条件の下で一つの活動は労働となるのか?
「報酬が得られる時」といったら、家事労働は含まれなくなってしまうなぁ・・・。保留。
■ 人は何によってある出来事が歴史的であると認識するのか?
それまでと違う何かが起こったと感じた時。
■ 人間の自由は労働の必要性によって制限されるか?
労働することで得られる自由もあると思います。
■ 人は知識なしに技能的習熟を持ちうるか?
できればカッコイイですね!
■ 正義の支配を実現するとは、単に法律を適用することか?
「正義の支配」という言葉自体、すでに胡散臭さを感じます。法律も、良いものばかりとは限りません。
■ 人は美を判断するのか、それとも感知するのか?
判断によって「処理」されて作られた美は美でなくなっていくように思います。という訳で「感知」に一票。
■ 法律は我々に何をするのが正しいかを示しているか?
法律を決める立場にある方々には、法律を守ることによって世の中がどう転がっていくかを想像して法律を作ってもらいたいものだと思います。
■ 他人に対してのみ義務はあるのだろうか?
そんなことはないでしょう。自分に対するものもあるはずです。
■ 時間から逃れようすることには意味があるのだろうか?
「時間から逃れる」ってどういう状態を言っているんでしょうね?「時間を忘れる」のであれば普通に通常起こっているし、「時間を歪ませることができるようにする」のであれば、それができたら途轍もなくスゴイことです。
■ ある文化の価値を客観的に評価することは可能だろうか?
あまり「客観」という言葉を信じていません。
■ 経験が何かを証明することが出来るか?
証明かどうかはわかりませんが、とりあえず「説得力」は増す気がします。
■ 真理よりも幸福を優先すべきだろうか?
真理を得ることが幸福だと考える人もいるのでは?その場合は共存しているといえるのでは?
■ ある特定の文化が普遍的な諸価値の担い手となり得るだろうか?
そういう考えはアブナイと思います。
* * *
ふぅ。
バカロレアはパスできそうもないなー。(^_^;)
2007.6.3
sync
sync(2004年〜)
http://www.akiyo.jp/sync/
音と動きを同時にレイアウトできる装置。
* * *
初めに正直に告白しておきましょう。この作品はコンセプトから実際の制作に移る段階で破綻しているのです。
2001年9月11日、ニューヨークで起こったショッキングな事件を皮切りに、世界はキナ臭い雰囲気に包まれるようになってきました。メディアを通じて伝えられてくる「エライ人たち」の言葉は実感の持てるものではなく、かと言って自分が何をしていいのか、何ができるのかもわからず悶々とした気持ちが続いていました。
いち早く、自分の見解を世に示して運動を起こした人たちもいました。その中には私の好きな著名人の方も何人かいました。彼らの運動に協力するというのも一つの方法だったと思います。でも、なんとなく「私のやり方」ではないのでは、と思ってしまったのです。あまりにも複雑な状況と伝わってくる情報に対して、自分の中で納得する答えが見つけられないで困惑していただけかもしれません。
そんな中でフと思ったのです。「指導者」たちからでもなく「メディアの誘導」からでもなく、普通の人が普通になんとなく感じていることの方が、ずっとマトモなものなのではないか、と。
良い例えになっているのかどうか、わかりませんが。
ある場所に住む猿が、ある時海水で食べ物を洗い始めたそうです。食べ物に若干の塩味がついている方が美味しいと感じたからなのでしょうか。ほぼ時を同じくして、別の場所に住む猿たちも海水で食べ物を洗うことを好みはじめたとか。
「偶然の一致」「進化の過程」いろんな言葉で表されるかもしれませんが、とにかく彼らは示し合わせた訳でもなく同じ行動をとり始めたのです。
「普通に感じること」「同じように感じること」の中には気付かないうちにすり込まれていることだってあるでしょう。社会の中で生活している限りは、それがない方が難しいと思われます。それでも、立ち止まって辺りを見渡しながら考えてみて、出てくる答えがメディアを通じて流れている意見と違うところで一致することだってあるはずです。
完全な一致ではなくて、個々は思い思いに動いているのに、なんとなく全体を見渡してみると妙な同調が生まれている感じでもよさそうです。偶然思い出した昔演奏したことのあるメロディを奏でていたら、仲間たちもポツポツ加わってきて、気付いたらみんなでその曲を演奏していた、という感覚にも少し似ています。
そんな「フとした同調感覚」を表現できないかと考えはじめたのがこの作品を作るきっかけでした。
* * *
コンセプトを表現に置き換えていく作業は時には強い葛藤を伴います。すんなりと行く場合もあるのですが。
この作品を作っているときには、それまでにないくらい強い葛藤を感じました。「伝えたいことをわかりやすく伝えること」と「キレイだと感じて表現したいこと」が全くかみ合わなかったのです。
そして、私は後者を選択してしまいました。
おそらく、それまでの虚脱感や困惑や心の同調を表現したいのであれば、別の表現があったはずなのです。
* * *
『sync』は作品としても完成できていません。
そして私は相変わらず困惑したままなのです・・・。