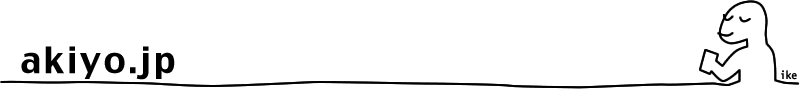2005.6.21
デジタル・キノコの生える場所
以前、読んだ話より。
キノコの胞子というものは、とても微細なもので、空中に浮遊しているものである。それが、条件のいいときに菌糸となり、キノコとしての姿をあらわす。
その条件とは。例えばある場所に、通常撒かれることのないような物質(そこであげられた例は尿でしたが・・・)を撒いてみる。すると、それに刺激を受けた、いつもとはちがうキノコがワラワラと生えてきた、とのこと。
この話を読んだとき、なんだか建築に似ていると思った。ある敷地に安藤忠雄や内藤廣を撒いてみる。(失礼な表現をしてスミマセン!)すると、それに反応した建築が「生えて」くる。そう考えることもできるのではないか、と。
最近の私はコンピュータに向かっての作業が多い。それも、前提条件があるわけではなく、自分の中でモヤモヤとしているものを具象化するような作業。そして、ふと思った。「キノコはどこから生えてきているのか?」
「自分の記憶から」としか言いようがない気がした。それもかなり純化された状態であらわれる。それが面白くもあり、怖くもあり。モノを創っている人にとってはそれが普通なのかもしれない。ただ、私にとっては、少々違和感のあることだったのだ。
なにも、デジタルに限った話ではないかもしれない。それでも実体のあるものを創っている人は、多かれ少なかれ素材などから触発される部分があるのでは?・・・どうなんでしょう。このへんの話は是非聞いてみたいところ。
何にしても、宿主(?)の記憶を純度の高い状態のキノコとして効果的に発生させることが出来たら。・・・いいよなぁ。
【旧 Short Tripより 1999.09.01】